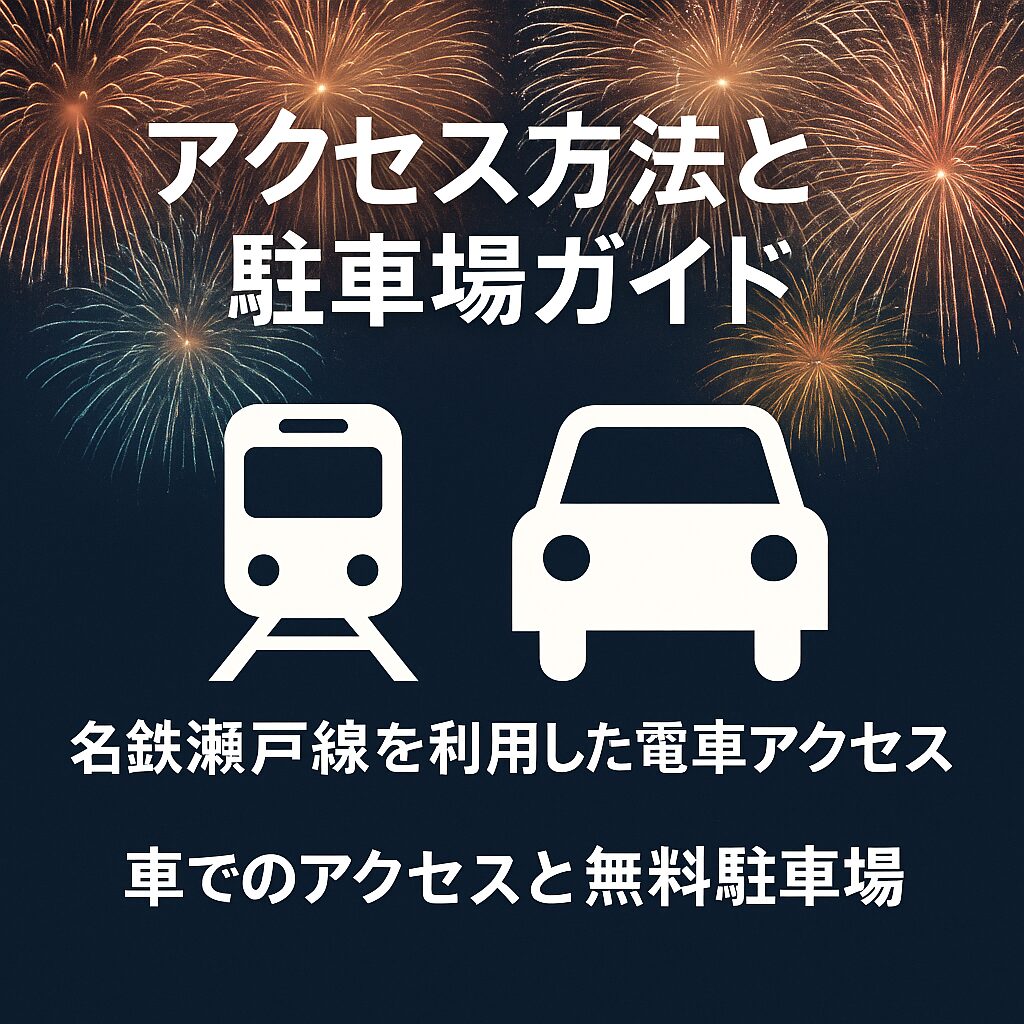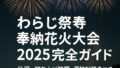秋といえば花火!でも、「どこに行けばいいか迷う…」「混雑が心配…」という方におすすめなのが、愛知県瀬戸市で開催されるせともの祭2025。全国最大級の陶器市として知られるこのお祭りでは、初日の夜に約1,000発の花火が打ち上がり、夜空を彩ります。本記事では、花火の打ち上げ日程・時間・アクセス方法・混雑対策・持ち物チェックリストまで、初めてでも安心して楽しめる完全ガイドをお届けします!
せともの祭花火2025の日程と基本情報
開催日はいつ?2025年のスケジュール
2025年の「せともの祭」は、9月13日(土)と14日(日)の2日間にわたって開催されます。例年9月の第2週末に開催されるこのイベントは、全国から観光客が訪れる愛知県瀬戸市の一大行事。2025年は第94回目の開催となり、これまでの伝統とにぎわいがさらにパワーアップすると期待されています。中でも注目されているのが、初日の夜に行われる花火大会です。
この花火大会は、陶器市や屋台のにぎわいが最高潮になる夕方の時間帯に行われ、祭りの盛り上がりを華やかに締めくくる存在。花火の打ち上げは1日限りなので、日程はしっかり確認しておきましょう。雨天の場合は翌日14日(日)に順延される予定です。天候に左右されるため、当日は公式情報やSNSで最新の開催状況をチェックすることをおすすめします。
地元の人だけでなく、遠方から来る人も多いこのイベント。日程に合わせてホテルや交通手段を早めに予約しておくと安心です。特に花火をメインに訪れる場合は、13日(土)の午後から夜にかけてが最も混雑します。スケジュールに余裕を持った訪問計画が、快適な観覧のコツです。
花火打ち上げ時間と発数の詳細
2025年のせともの祭での花火打ち上げは、9月13日(土)18:25~18:45の約20分間で実施予定です。打ち上げ時間は例年ほぼ固定されており、夕暮れ時にスタートして夜空に映える花火が楽しめます。短い時間ながら約1,000発もの花火が集中的に打ち上げられるため、迫力と密度はかなりのもの。
地元の有志や企業が協賛するスターマインや、フィナーレの連続打ち上げなど、見どころも盛りだくさん。打ち上げ場所は瀬戸川沿いのエリアが中心で、広範囲から見ることができますが、観覧スポットの確保は早めに動くのが鉄則です。
特に人気のエリアは、名鉄尾張瀬戸駅から徒歩圏内の川沿いベンチや橋の上。ここは見晴らしがよく、ローカル感も味わえるおすすめスポットです。観覧場所によっては音と光の迫力に差が出るので、好みの鑑賞スタイルに合わせて選んでください。
荒天時の延期日程と注意点
せともの祭の花火は、雨天や強風など荒天時には翌日9月14日(日)に延期されます。天候によっては直前に開催可否が決まるため、公式ホームページやSNS(瀬戸市公式アカウントなど)での情報収集が重要です。
延期される場合でも、打ち上げ時間は基本的に同じく18:05~18:25を予定しています。つまり、14日に花火が行われる可能性もあるため、2日間とも予定を空けておくと安心です。
また、延期に伴い交通機関や周辺店舗の営業時間が変更になることもあります。駐車場の混雑状況にも影響が出るため、当日の天気とあわせてリアルタイムの混雑情報もチェックしておくとよいでしょう。スマートフォンで確認できるアプリやSNS活用が便利です。
会場の場所とエリア概要
せともの祭の主な会場は、名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」周辺およびその北側に広がる市街地一帯です。駅を降りてすぐに陶器市のブースや屋台、イベントスペースが立ち並び、お祭りムード一色。瀬戸市役所付近から川沿いまで広く会場が広がり、歩行者天国になっているエリアも多く見られます。
花火の打ち上げは瀬戸川河川敷周辺で行われるため、駅から徒歩10分以内でアクセス可能な好立地。会場全体がコンパクトにまとまっており、移動しやすいのもこの祭の魅力です。
一部有料観覧エリアや交通規制区間もあるため、事前に公式マップを確認しておくとスムーズです。特に花火を見るために場所取りをする場合は、地面がぬかるまないエリアやトイレの近くを選ぶと快適に過ごせます。
せともの祭ならではの特徴
せともの祭は、ただの花火大会ではありません。日本三大陶器市の一つとして知られるこの祭は、陶磁器の展示即売会が中心に行われ、地元の窯元や作家たちが自慢の品を持ち寄ります。全国から焼き物ファンが集まり、普段手に入らない一点物の器を探す人も多数。
また、食べ歩きが楽しめる屋台も充実しており、瀬戸市ならではの「瀬戸焼そば」やご当地グルメも登場します。お祭りの賑わいの中で、美味しいものとお気に入りの陶器に出会えるのも魅力の一つです。
そして何よりも、昼間の陶器市から夜の花火への流れがとてもドラマチック。日中から訪れて、たっぷりと瀬戸の魅力を堪能したあとに、夜空を彩る花火で締めくくるという最高の流れが、毎年多くの人に愛されています。
アクセス方法と駐車場ガイド
名鉄瀬戸線を利用した電車アクセス
「せともの祭」へは公共交通機関を利用するのが断然おすすめです。特に便利なのが、名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」。この駅は祭り会場の中心に位置しており、改札を出た瞬間からイベントのにぎわいを体感できます。駅から会場までは徒歩0分。すでに陶器市のブースや屋台が立ち並んでおり、移動ストレスがまったくありません。
名古屋方面から向かう場合は、名鉄瀬戸線の始発駅である**「栄町駅」**から乗車して約50分で到着。栄町駅は名古屋市営地下鉄の「栄駅」とも直結しているので、地下鉄を使ってのアクセスも良好です。
花火の時間帯に近づくと、駅構内は非常に混雑します。行きは早めの到着を心がけ、帰りはピークを外すことで快適な移動が可能です。ICカード(manaca、TOICA、Suicaなど)を事前にチャージしておくと、券売機での行列を回避できます。
臨時列車の増発がある年もあるので、最新の運行情報は名鉄の公式サイトや駅掲示をご確認ください。
車でのアクセスと主要ICからの所要時間
車で「せともの祭」に行く場合、主に利用されるインターチェンジは次の2つです。
| インターチェンジ | 所要時間(目安) | 主な経路 |
|---|---|---|
| せと赤津IC(東海環状道) | 約10分 | 国道155号線経由 |
| 長久手IC(名古屋瀬戸道路) | 約15分 | 瀬戸街道(県道61号)経由 |
「せと赤津IC」は瀬戸市内に最も近く、花火会場へのアクセスにも優れています。ただし、花火のある初日の夕方は周辺道路が非常に混雑するため、午後2時までの到着を目指すとベストです。
カーナビを利用する場合は「瀬戸市役所(愛知県瀬戸市追分町64-1)」や「尾張瀬戸駅」を目的地に設定すると便利です。ただし、会場周辺には交通規制が敷かれるため、途中で迂回を求められる場合もあります。
無料駐車場の場所と台数
せともの祭では、市内各地に約1,000台分の無料駐車場が用意されます。代表的な駐車場は以下のとおりです。
| 駐車場名 | 収容台数 | 会場までの距離(徒歩) |
|---|---|---|
| 瀬戸市役所駐車場 | 約200台 | 約10分 |
| 陶原公民館 | 約100台 | 約15分 |
| 水無瀬中学校 | 約150台 | 約15分 |
| 文化センター | 約200台 | 約12分 |
| 窯神グラウンド | 約150台 | 約20分 |
ただし、午後3時以降はほとんどの駐車場が満車になります。できるだけ午前中〜昼過ぎまでに到着するのが鉄則。遠方から来る方は、近隣市の駅周辺に停めて電車でアクセスする「パーク&ライド」も検討しましょう。
駐車場利用の混雑ピーク時間
駐車場は、特に午後3時〜5時が混雑のピークです。この時間帯には、瀬戸市内の主要道路でも渋滞が発生しやすく、現地に到着しても駐車場探しで時間を取られてしまうことがあります。
また、花火終了後の午後7時〜8時半頃は、駐車場から出る車で周辺道路が詰まるケースが多発します。スムーズに帰るためには、花火が終わる前に車へ向かうか、会場で1時間程度ゆっくりしてから出発するのがコツ。
トイレや買い物なども混雑に含まれるため、トイレ休憩は早め・余裕を持って取るのがおすすめです。なお、バイクや自転車で来る方には専用の駐輪スペースがある場合もありますが、事前にチェックしておきましょう。
公共交通を使うメリット
せともの祭では、公共交通を利用することで時間のロスや駐車ストレスを大幅に減らすことができます。特に名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」からは、降りてすぐに会場入りできる利便性が魅力です。
また、花火終了後の大渋滞や出庫ラッシュを避けるうえでも、電車でのアクセスは非常に有効。名鉄では例年、臨時列車や増便が行われることもあり、乗り遅れの心配も少ないのが特徴です。
さらに、公共交通を利用すれば、飲食やアルコールを楽しめる自由度も増します。せともの祭では屋台グルメが充実しているため、飲み歩きを楽しみたい方には公共交通が最適です。
交通系ICカードを事前にチャージし、混雑時のスムーズな入出場を意識すると、快適さがさらにアップします。
混雑回避のコツと穴場スポット
花火開始前後の混雑ピークを避ける方法
せともの祭の花火大会は、例年約3万人以上が観覧に訪れる人気イベント。そのため、午後4時以降から花火終了後までが最も混雑する時間帯になります。この時間帯は駅周辺・道路・会場内すべてが人であふれかえり、移動も困難になることがあります。
混雑を避けるためには、まず「到着時間を早める」のが最も効果的です。おすすめは午後1時〜2時までの到着。この時間なら、まだ余裕をもって駐車場や観覧場所を確保できます。
また、花火が終わった瞬間は一斉に帰路につく人が多く、駅や駐車場が大混雑します。帰りを少し遅らせて、20時ごろまで会場でのんびり過ごすのも混雑回避のコツです。陶器市の夜営業ブースや屋台を楽しみながら、ゆったりと時間調整をすると良いでしょう。
子連れやファミリーにおすすめの鑑賞エリア
子連れやファミリーで訪れる場合は、座って観られる・トイレが近い・混雑が少ないという3つの条件を満たしたエリアを選びたいところです。おすすめは以下のエリアです。
-
瀬戸市文化センター前の広場:スペースが広く、子ども連れでも安心。仮設トイレも近くにあり便利です。
-
瀬戸市役所周辺の川沿い:比較的ゆったりしており、ベンチや芝生スペースも利用可能。
-
瀬戸川下流エリア(赤津方面):メイン会場から少し離れているため、人が少なく穴場です。
ベビーカーでの移動も考慮するなら、段差の少ない会場内の歩行者天国エリアが安全です。暑さ対策や虫除けグッズの持参も忘れずに。
また、小さなお子様がいる場合は花火の音が苦手な場合もあるため、耳栓やイヤーマフがあると安心です。途中で音に驚いて泣いてしまう子も多いため、事前の準備が大切です。
「窯垣の小径」など落ち着いて見られる穴場
混雑を避けて、静かに花火を楽しみたい人には**「窯垣の小径」**がおすすめです。ここは瀬戸の伝統的な焼き物の壁が続く風情ある散歩道で、花火の打ち上げポイントからはやや離れているものの、静かな環境で鑑賞できるスポットとして人気があります。
場所は尾張瀬戸駅から徒歩約20分ほど。やや歩きますが、そのぶん混雑もなく、落ち着いた雰囲気で花火を楽しめます。写真撮影にも適した場所が多く、インスタ映えする背景とともに花火を収めたい人にもぴったりです。
その他の穴場としては、次のような場所もあります。
-
名鉄瀬戸線「水野駅」周辺の高台
-
瀬戸公園(少し高台にある自然公園)
-
品野陶磁器センター周辺(遠景で楽しむスタイル)
いずれも混雑が苦手な方、写真や動画をしっかり撮りたい方におすすめのスポットです。
花火終了後のスムーズな帰り方
花火終了後は、尾張瀬戸駅に数千人が一斉に向かうため、非常に混雑します。スムーズに帰るにはいくつかの選択肢があります。
-
花火が終わる5分前に移動開始する
ピーク前に移動すれば、駅や駐車場での混雑を避けられます。 -
会場内で1時間ほど時間をつぶす
屋台で夜ごはんを食べたり、夜店を回ってのんびり過ごすことで、混雑が落ち着く20時以降に動くのがおすすめです。 -
隣駅(新瀬戸、水野)まで歩いて乗車する
尾張瀬戸駅を避け、少し歩いて隣駅から乗れば空いている可能性が高いです。 -
宿泊して翌日に帰る
余裕のある方は瀬戸市または名古屋市内に宿泊して、翌朝のんびり帰るのも快適な選択肢です。
どの方法を選ぶにしても、子ども連れや高齢者が一緒の場合は、早め早めの行動が安心です。
トイレや休憩場所のチェックポイント
花火大会当日は人が多く、仮設トイレの行列が長くなるのは避けられません。快適に過ごすためには、あらかじめトイレの場所を把握しておくことが大切です。以下は代表的な設置場所です。
-
瀬戸市役所周辺(常設トイレ+仮設)
-
瀬戸川沿いの広場(仮設トイレ多数)
-
陶器市ブースの中間地点(簡易トイレあり)
-
文化センターや公民館(休憩所兼トイレ)
休憩場所としては、瀬戸市文化センターや市民会館などの屋内施設が便利です。暑さ対策や急な雨への避難にも役立ちます。
お年寄り連れや小さな子どもがいる場合は、こうした「室内休憩ができるポイント」を事前にチェックしておきましょう。特に花火終了前後はトイレも休憩所も混雑するため、夕方までに1回トイレを済ませておくのが安心です。
せともの祭をもっと楽しむ過ごし方
陶器市でのお得な買い物テクニック
せともの祭最大の目玉のひとつが、全国的にも有名な大規模な陶器市です。瀬戸焼をはじめ、さまざまな焼き物が特別価格で販売され、普段は手に入らない作家モノや掘り出し物が並びます。
まず狙い目の時間は、午前中の早い時間帯。人気の作品や一点モノはすぐに売れてしまうため、早めの行動がポイントです。また、2日目(日曜日)の午後には一部で値下げ交渉やセール価格になる店舗もあるため、タイミングを見て再訪するのもおすすめです。
価格交渉については、基本的には「おまけ」や「セット価格」で対応してくれるお店が多い印象。「複数買うので少しお安くなりますか?」と、丁寧に聞くのがコツです。
さらに、お買い物の際にはエコバッグや新聞紙、緩衝材を持参すると便利です。お店でも包んでくれますが、自分でも持っていると安心。大きな器や花瓶などを買う予定がある方は、キャリーカートや大きめのバッグもおすすめです。
人気の屋台グルメとおすすめメニュー
せともの祭はグルメも充実!屋台の出店数は数十店以上にのぼり、定番から地元ならではの味まで、幅広く楽しめます。
中でも人気のメニューは、瀬戸市名物の**「瀬戸焼そば」**。しっかり味のついた濃厚なソースに、もちっとした太麺が特徴のローカルフードです。他にも地元の食材を使った串焼きや、名古屋名物の味噌カツ串、どて煮などもおすすめ。
スイーツ系も充実していて、フルーツ飴や冷やしパイン、かき氷など、暑さ対策にもぴったり。近年では映えるスイーツやドリンクも多く、インスタ映えスポットも会場内に設置されていることがあります。
また、ビールやチューハイなどのアルコール販売もあるため、公共交通機関で来場すれば屋台飯をつまみにゆっくりと楽しめます。特に花火前の時間帯は混雑するため、夕方5時前には食事を済ませるのがスムーズです。
会場で楽しめるイベントや企画
せともの祭は陶器市と花火だけではありません。会場内では、地元学生や団体によるステージパフォーマンスや、子ども向けワークショップなど、誰でも楽しめる企画が盛りだくさんです。
過去には、以下のようなイベントが開催されています:
-
郷土芸能や和太鼓の演奏
-
ご当地キャラとの撮影会
-
陶芸体験コーナー(絵付け・ろくろ体験)
-
フリーマーケットやアート作品の販売
-
市内高校の吹奏楽演奏やダンスショー
特に家族連れには、子ども向けの陶芸体験が人気です。短時間で完成し、後日郵送してくれるコースもあるので、お土産にもなります。
花火が始まるまでの時間を、こういったイベントで楽しく過ごすと1日中飽きずに楽しめます。イベントスケジュールは当日配布されるパンフレットや、瀬戸市の観光公式サイトでも確認できます。
見どころを効率よく回るモデルコース
せともの祭は広範囲で開催されるため、計画的に回るのが大切です。以下はおすすめの1日満喫モデルコースです。
| 時間帯 | 行動内容 |
|---|---|
| 10:00〜12:00 | 尾張瀬戸駅到着→陶器市めぐり(人気店を先にチェック) |
| 12:00〜13:00 | 屋台で昼食(瀬戸焼そばやどて煮など) |
| 13:00〜15:00 | 陶芸体験やアートブースを散策 |
| 15:00〜16:00 | 文化センター周辺で休憩・買い物 |
| 16:00〜17:30 | 屋台で夕食→観覧場所へ移動 |
| 18:25〜18:45 | 花火観覧 |
| 19:00〜20:00 | 夜の屋台めぐりorゆっくり帰宅 |
混雑を避けつつ、陶器市・グルメ・イベント・花火をフルで楽しむ流れです。子ども連れの場合は、もう少しゆとりをもたせて休憩時間を増やすと良いでしょう。
カップル・家族連れで楽しむポイント
せともの祭はカップルにもファミリーにも大人気。目的に合わせた楽しみ方をすることで、より思い出深い1日にできます。
【カップルにおすすめ】
-
昼間の陶器市でお揃いの食器を探す
-
花火は「窯垣の小径」など静かなスポットで観覧
-
夕暮れ時の瀬戸川を散歩して風情を楽しむ
【家族連れにおすすめ】
-
陶芸体験や子ども向けワークショップに参加
-
屋台で子どもが楽しめるゲーム(ヨーヨー釣り、射的など)
-
トイレや休憩所に近い場所で観覧準備を整える
どちらのスタイルでも、「午前中からしっかり回る」「帰りの混雑を見越して行動する」ことで快適に楽しめます。
初めてでも安心!持ち物&事前準備チェックリスト
花火観賞に必須の持ち物リスト
せともの祭の花火を快適に楽しむためには、事前の持ち物準備がとても大切です。特に長時間屋外にいることを想定して、以下のアイテムは必ず準備しておきましょう。
| 持ち物 | 理由 |
|---|---|
| レジャーシート | 地面に座るため。防水タイプがおすすめ |
| 折りたたみ椅子 | 長時間の待機や観覧に便利 |
| 虫除けスプレー | 河川敷や草地で蚊に刺されやすいため必須 |
| ウェットティッシュ | 食事や手洗い代わりに使える |
| モバイルバッテリー | 写真・動画撮影でスマホの電池消費が激しい |
| 飲み物(ペットボトル) | 屋台で買うのもOKだが混雑時のために持参推奨 |
| 軽食・お菓子 | 小腹が空いたときに助かる |
| ごみ袋 | 自分のゴミは持ち帰るマナーとして必要 |
これらをまとめて入れられるリュックサックや大きめのトートバッグがあると移動もスムーズです。特に座りながら花火を観る場合、レジャーシートやクッション性のある座布団があると快適度が一気に上がります。
小さなお子様連れに便利なグッズ
小さな子どもと一緒にせともの祭に行くなら、通常の持ち物に加えて子ども向けの便利アイテムも忘れずに準備しましょう。
-
ベビーカー:長時間の移動でも子どもの負担を軽減。混雑時は折りたたみタイプが便利
-
着替えセット:汗をかいたり食べ物で汚れることも多いので1セットあると安心
-
おやつ・飲み物:待ち時間にぐずり対策として必須
-
おむつ・おしりふき:トイレの場所によっては替えづらいことも
-
ポータブルおむつ替えシート:地面や椅子の上で使える携帯型が便利
-
子ども用耳栓やヘッドホン:花火の音が苦手な子どもには必須アイテム
また、迷子対策として連絡先を記載したネームタグや、親子でおそろいの服・目立つ色の帽子などを身に付けておくと安心です。
混雑時に役立つアイテム
人混みの中では、ちょっとしたアイテムが大きな差を生むことがあります。以下は混雑対策用の便利アイテムです。
-
小さな懐中電灯 or スマホライト:夜道や足元を照らすのに便利
-
扇子やハンディ扇風機:暑さ対策として必須
-
マスク(使い捨て or 布):人混みや屋台の煙が気になる人に
-
アルコール除菌スプレー or ジェル:屋台利用時などに重宝
-
財布は小型のものに:貴重品は最小限で体に密着できるように
また、財布やスマホなどの貴重品は体の前にかけられるボディバッグや斜め掛けバッグに入れると安心です。リュックよりもスリ対策になります。
当日の服装と気温対策
9月中旬の瀬戸市は、日中はまだ30℃近くまで気温が上がることもありますが、夜になると一気に涼しくなる日もあります。そのため、体温調節しやすい服装が理想的です。
-
日中:通気性の良いTシャツ+帽子や日傘で日差し対策
-
夜間:薄手のカーディガンやストールで寒さ対策
-
靴:長時間歩くのでスニーカーや履き慣れた靴が安心
-
雨天時:折りたたみ傘やレインコートも準備しておくと◎
また、女性や子どもは浴衣で来場する人も多いですが、歩きにくくなったり暑さでバテやすくなることも。着替えや歩きやすい靴を用意しておくと安心です。
スマホ撮影で花火を綺麗に撮るコツ
せっかくの花火、綺麗にスマホで撮影したいですよね。でも、ぶれてしまったり、ピントが合わなかったり…そんな時は以下のコツを使ってみてください。
-
三脚 or スマホスタンドを使う
安定した画角でぶれずに撮影できます。 -
カメラアプリの「夜景モード」を使う
自動でシャッタースピードや明るさを調整してくれます。 -
連写 or 動画モードで撮影する
一番綺麗な瞬間を逃さず収められます。 -
露出を少し下げる(暗めに設定)
夜空の中でも花火の光が綺麗に映えます。 -
人混みの頭が映らないように高めの位置から
観覧エリアの後方や段差のある場所を狙うと◎
InstagramやSNSにアップするなら、**ハッシュタグ「#せともの祭2025」「#瀬戸花火」**などを活用すると、他の人の投稿も見つかって楽しめます。
まとめ:2025年のせともの祭花火を120%楽しむために
2025年のせともの祭は、9月13日(土)と14日(日)に開催され、13日には大注目の花火大会が行われます。約1,000発が夕暮れの空に打ち上がるこの花火は、陶器市や屋台のにぎわいとあいまって、まさに秋の瀬戸を象徴する風物詩です。
アクセス手段としては、名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」の利用がもっともスムーズ。駐車場も用意されていますが、混雑を避けるなら公共交通機関の活用が断然おすすめです。花火の混雑対策には、早めの行動や穴場スポットの利用、帰宅時間のずらし方がカギとなります。
せともの祭の魅力は花火だけではありません。日本三大陶器市としてのスケールや、瀬戸ならではの焼き物の出会い、ご当地グルメやイベントの数々も見逃せません。家族連れ・カップル・友人同士、それぞれに合った楽しみ方ができるのがこのお祭りの素晴らしいところです。
持ち物の準備や服装、スマホ撮影のコツまでを押さえれば、はじめての方でも安心して1日を満喫できるはず。今年の秋は、ぜひ「せともの祭」で最高の思い出を作ってください。