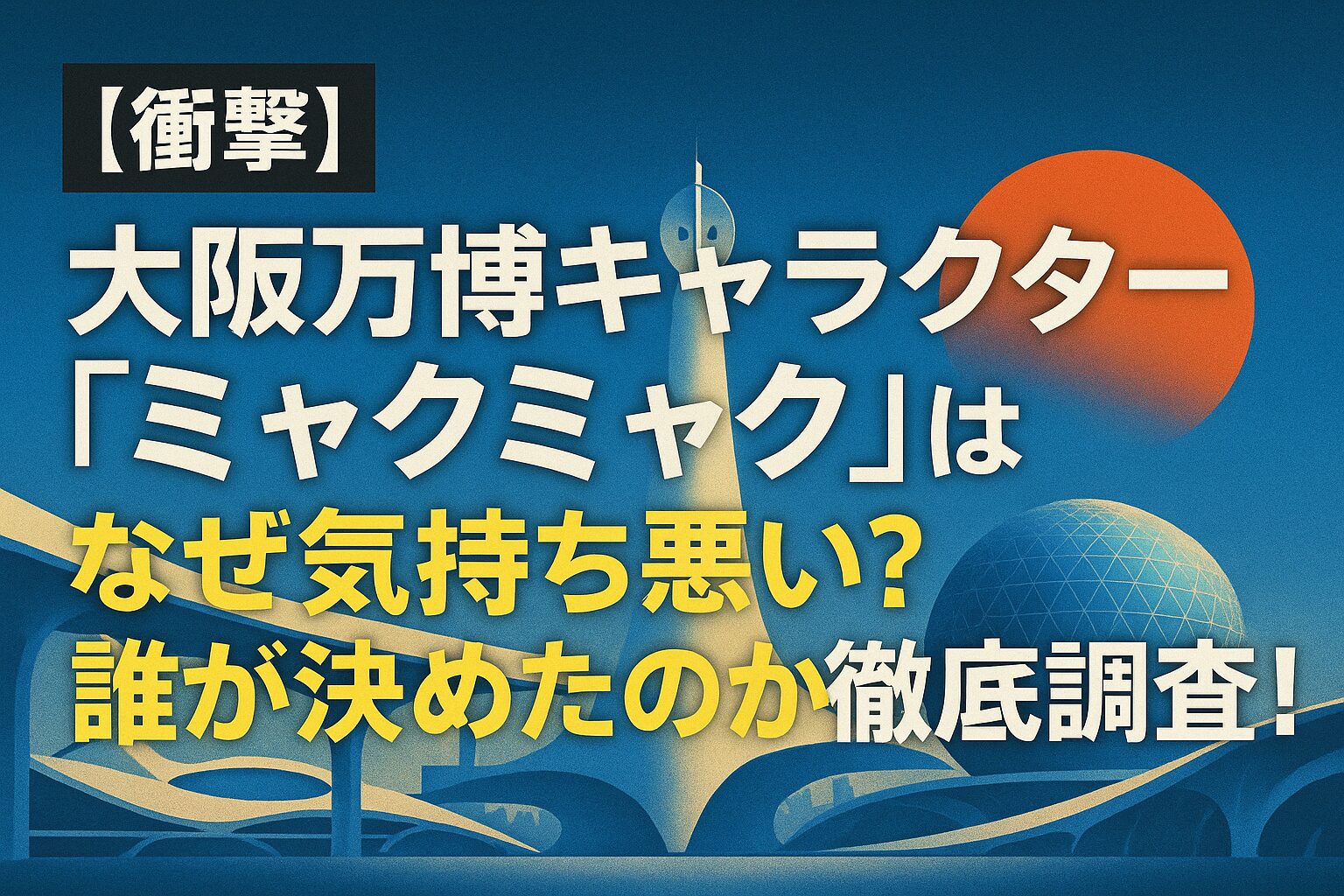2025年の大阪・関西万博。その公式キャラクター「ミャクミャク」が発表されるや否や、SNSやニュースで大きな話題を呼びました。「気持ち悪い!」「怖い!」「なぜこれを選んだの?」という声が続出する中、実はこのデザインには深い意図とストーリーが隠されていたのです。この記事では、ミャクミャクの正体や選定の舞台裏、国内外の反応を徹底調査!あなたの知らないミャクミャクの魅力が、きっと見えてくるはずです。
大阪万博キャラクター「ミャクミャク」って何者?
公式プロフィールとコンセプトとは?
2025年の大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」は、2022年7月に発表されて以来、強烈なインパクトで話題を集めました。そのデザインは一度見たら忘れられない、青と赤の球体が合体したような姿をしています。
ミャクミャクの公式プロフィールでは、「細胞」と「水の精」が融合してできた生命体であり、”水の都・大阪”を象徴する存在だとされています。また、公式には「ミャクミャク様」とも呼ばれ、人格を持つキャラクターではなく、「形の変わる存在」として表現されています。これにより、アニメ的な可愛さよりもコンセプト重視のデザインになっているのです。
名前の「ミャクミャク」は、日本語の「脈々(みゃくみゃく)」という言葉から取られています。「伝統が脈々と受け継がれる」などの意味があり、大阪や日本の歴史・文化・技術が未来へと続く様子を表しているとのことです。
コンセプトは深く、テーマに沿ったクリエイティブなキャラクターであることが分かりますが、初見で戸惑う人が多かったのも事実です。
見た目のインパクトはなぜこうなった?
ミャクミャクの見た目の最大の特徴は、赤い球体がいくつも連なった「血管」や「ウニ」のような不思議な造形と、頭部に乗っている青い顔です。目が2つあり、赤い部分は自由に動く設定ということで、デザインとしての動的な面白さはありますが、全体のバランスに驚く声が多く聞かれました。
このデザインは、いわゆる「マスコットらしさ」をあえて外しており、強いメッセージ性と独自性を打ち出しています。つまり、可愛いかどうかではなく、「記憶に残る」ことを目的とした設計だったのです。
アート的な要素を重視した結果、従来のゆるキャラとは一線を画すものになったとも言えるでしょう。
名前の意味と由来に注目
「ミャクミャク」という名前には深い意味が込められています。「脈々と受け継がれる」という日本語の慣用句から取り、古来からの文化・技術・精神が未来に向かって流れ続ける様子を表しています。
また、この名前は子どもにも覚えやすく、発音もしやすいという利点があります。ひらがな表記にしたことで親しみやすさも増しており、名前自体に対する評価は概ね良好です。
ただし、「音が可愛いのに見た目が怖い」というギャップに戸惑う声も少なくありません。
「血管」「ウニ」「妖怪」?ネットの第一印象
SNSではミャクミャク発表直後から、「血管のかたまりみたい」「ウニに顔がついてる」「妖怪じゃないの?」などの感想が多く飛び交いました。
以下は、X(旧Twitter)でよく見られたコメントの例です:
| 感想カテゴリ | 投稿の一例 |
|---|---|
| 見た目が怖い | 「子どもが泣きそう」「夜に見たらトラウマ」 |
| 意外と好き | 「クセになる」「見慣れると愛着わく」 |
| デザインに疑問 | 「なぜこの見た目で通った?」「審査員正気か?」 |
このように、第一印象は賛否両論でしたが、とにかく「話題性」が非常に高く、日本中が注目したことは間違いありません。
実はアート作品としての評価もある?
一方で、アートやデザインの専門家からは一定の評価もあります。特に現代アートの視点から見ると、「挑戦的」「前衛的」「記憶に残るアート」として評価されているようです。
実際、ミャクミャクを手がけたのは、現代美術家・山下浩平さんを中心とするクリエイティブチーム「mountain mountain」です。山下氏は「普通ではない視点から未来を表現したかった」と語っています。
アートとして見ると、「不気味さ」もあえて狙った意図的な表現であり、従来のゆるキャラ文化に対するアンチテーゼとも言えるかもしれません。
「気持ち悪い」「怖い」と言われる理由
視覚的に不快とされるデザインの特徴とは?
ミャクミャクが「気持ち悪い」と言われる最大の理由は、赤い球体が連なった有機的なデザインにあります。この形状が人間の「血管」「臓器」「ウニ」など、生命の中身やグロテスクな要素を想起させてしまうのです。
特に、視覚心理学の観点では、人は「規則性があるけれど少し歪んでいるもの」に違和感や恐怖を感じる傾向があります。ミャクミャクの形状はまさにこのパターンに当てはまっており、不快感を引き起こしやすいのです。
加えて、表情が一定で無機質な印象を与えるため、「魂のこもっていない人形」や「妖怪」的な怖さも感じさせる要因となっています。
SNSや掲示板のリアルな声を紹介
ミャクミャクの発表直後、X(旧Twitter)、5ちゃんねる、Yahoo!コメントなどのネット掲示板では、その外見に対するリアクションが爆発的に拡がりました。特に目立ったのは、「気持ち悪い」「怖い」「トラウマになる」といったネガティブな意見です。
SNSでは、「大阪万博のキャラ、なんでこうなった?」と驚きの投稿が多数寄せられ、一時はトレンドにもランクインしました。特に子育て世代や保育関係者からは、「子どもが怖がって泣いた」という体験談も多くシェアされています。
一方で、匿名掲示板やXでは、こんな声も見られました。
-
「気持ち悪いけど、クセになる」
-
「初見で鳥肌立ったけど、だんだん好きになってきた」
-
「逆にこれくらい振り切ってるのがいい」
つまり、強烈な第一印象の裏には、「話題性」や「記憶に残るデザイン」という意味での評価も徐々に高まっている様子がうかがえます。
下記の表は、ネット上の反応をカテゴリごとに分類したものです。
| 反応カテゴリ | 投稿例 | 備考 |
|---|---|---|
| 否定派 | 「気持ち悪くて泣いた」「本当に怖い」 | 子どもや感受性の強い人に多い |
| 肯定派 | 「愛嬌がある」「斬新で良い」 | アート感覚や若者層に多い |
| 混乱派 | 「なぜこれが選ばれた?」「理解が追いつかない」 | 初見で困惑した人が多い |
| 慣れ派 | 「最初は無理だったけど今は平気」 | 継続露出で印象が変化 |
| ギャグ派 | 「どう見ても妖怪」「深夜に動き出しそう」 | ネタ化が進行中 |
このように、ミャクミャクは単なるマスコットではなく、ネット文化の中で一種の「ネタキャラ」として定着しつつあるのです。
子どもたちの反応はどうだった?
「子ども向けのイベントキャラ」として見ると、ミャクミャクの評価は一段と複雑です。発表当初から保護者たちの間では、「あの見た目で子どもたちは喜ぶのか?」という疑問が多く出ていました。
実際、各地の万博関連イベントや展示会で子どもたちがミャクミャクと触れ合う場面では、泣き出してしまう子もいたとの報告もあります。特に、着ぐるみの大きさや動きに驚いて後ずさりする場面が見られ、保護者からは「もっと親しみやすいデザインが良かったのでは」という声も。
一方、教育現場や保育園などでミャクミャクを紹介すると、反応は意外にもポジティブなこともあります。ぬりえや紙工作を通じてキャラクターに親しんだ子どもたちは、「かわいい」「変な形で面白い」と感じるようになる傾向も見られました。
また、2023年には「ミャクミャクダンス」など子ども向けの動画コンテンツも増え、アニメ風に加工されたバージョンのミャクミャクは、より親しみやすく、受け入れられている印象です。
つまり、最初のインパクトは強烈でも、継続的なメディア展開やコンテンツ化により、子どもたちの中でも「怖い」から「面白い」へと印象が変化しているようです。
「かわいい」との意見も?賛否の分かれ目
一見「気持ち悪い」とされがちなミャクミャクですが、「かわいい」と感じる人たちも一定数います。特に、近年の「キモかわいい」ブームとの親和性が高く、ユニークで非定型なキャラクターが支持を得やすい環境が整ってきていることが背景にあります。
若年層やZ世代の間では、「変わっていること=個性」ととらえられる傾向が強く、SNS上でも「逆にかわいい」「クセになる造形が良い」といった声が見られます。
ここで、可愛いとされる要素と気持ち悪いと感じる要素を対比してみましょう。
| 要素 | 「かわいい」と感じる人 | 「気持ち悪い」と感じる人 |
|---|---|---|
| 目の表情 | のほほんとして癒される | 感情がなくて不気味 |
| 色使い | カラフルで楽しい | 血のような赤が怖い |
| 動き | 不思議でユーモラス | うねうねして生き物っぽい |
| デザイン性 | 前衛的で個性的 | 有機的すぎて不快 |
| 名前の響き | 音が柔らかくてかわいい | 音と姿が合っていない |
このように、同じ特徴でも受け取り方によって評価が分かれるのがミャクミャクのユニークな点です。
不快感が逆に「印象に残る」という狙い
実は、ミャクミャクの不気味さは意図的なものだったと考えられています。2025年の万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」において、「命」の原点を想起させるような見た目にしたいという方針があったそうです。
生命を構成する細胞、血管、水…これらをモチーフにデザインされた結果、「生き物っぽさ」や「不快感」を伴うフォルムになったのです。しかし、この「不快感=記憶に残る」というマーケティングの観点も見逃せません。
近年の広告戦略では、「話題性」「バズる力」が重要視されており、ミャクミャクのように一発で印象づける存在は、むしろ効果的です。実際、発表後はテレビやネットニュースで連日報道され、名前と姿は瞬く間に全国へと浸透しました。
つまり、「気持ち悪さ」はマイナスではなく、話題を呼び、記憶に残し、コンテンツとして成長させるための「設計」だった可能性があるのです。
いったい誰が決めた?選定の裏側とは
キャラクターデザインの公募と審査プロセス
ミャクミャクは、実は一般公募によって選ばれたキャラクターではありません。2020年に「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(万博協会)」が、キャラクターデザインのコンセプト提案を非公開で募集し、参加したのは選ばれた6つの企業やクリエイティブチームでした。
その中から、最終的に選ばれたのが「mountain mountain」(マウンテンマウンテン)というクリエイティブユニットの案で、彼らが提出したコンセプトが高く評価され、正式に採用されました。
公募ではなく選定制だったため、「なぜこのデザインが選ばれたのか」という疑問が多く出た一方、実は高度な審査と意図的な選択があったことが分かっています。
制作したクリエイターはどんな人?
ミャクミャクを制作したのは、山下浩平さんを中心とした「mountain mountain」のチーム。山下さんは、アートディレクターやグラフィックデザイナーとして活躍しており、広告やアートの世界で独自の表現を追求している人物です。
彼はデザイン発表時のインタビューで、「可愛らしさだけではなく、未来を感じさせる多様性を表現したかった」と語っています。ミャクミャクの変幻自在なフォルムは、「変わり続ける存在」=未来の象徴として捉えられており、深い意味が込められています。
このように、デザインは単なる見た目ではなく、メッセージ性とコンセプトを重視して制作されたことがわかります。
審査委員会に名を連ねたメンバーとは
ミャクミャクのデザイン選考には、万博協会内の有識者やアート関連の専門家が多数参加しました。具体的な委員名はすべて公開されていませんが、審査には以下のようなジャンルの専門家が加わっていたと報告されています。
-
現代アートの研究者
-
ブランド戦略のコンサルタント
-
広告代理店のクリエイティブディレクター
-
地域文化に詳しい大学教授
-
万博協会の内部関係者
このような多様な視点から、「見た目」ではなく「理念」「独創性」「インパクト」といった点が重視され、ミャクミャクが選ばれたというわけです。
デザイン決定までの経緯を時系列で紹介
以下は、ミャクミャク誕生に至るまでの流れを簡単にまとめた時系列です。
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2020年12月 | 万博協会が非公開でデザイン提案を募集 |
| 2021年3月 | 6つの企業・団体に提案依頼 |
| 2021年6月 | 提案の中から1案に決定(mountain mountain) |
| 2022年7月 | キャラクター「ミャクミャク」正式発表 |
| 2023年〜 | 各種イベント、PR活動に本格登場 |
このように、約1年以上の選考期間を経て、細かい検討の上で決定されたことが分かります。安易な選定ではなく、戦略的かつ計画的に進められてきたプロジェクトだったのです。
批判は想定内?万博協会の公式コメント
ミャクミャクの発表後、あまりに多くの批判が殺到したことを受けて、万博協会は複数の場でコメントを発表しています。
特に注目されたのが、「すべての人に最初から受け入れられるとは思っていなかった」という発言です。これは、賛否を分けることを前提にしたデザインだったことを示唆しています。
また、「印象に残ること」「語られること」がキャラクターの目的であり、話題になることで大阪万博への注目を集めた点では、一定の成功だとする評価もあります。
このように、批判や賛否両論は「想定内の展開」だった可能性が高く、むしろ注目を浴びることこそが戦略の一部だったと考えられます。
海外ではどう見られている?国別の反応まとめ
欧米メディアの報道は意外な評価?
ミャクミャクのインパクトは海外にも波及し、特に欧米メディアでは「奇抜な日本文化の象徴」として大きく取り上げられました。イギリスのBBCやアメリカのCNNなどが紹介し、「日本らしいユニークさ」「前衛的なデザイン」と報じたことで話題になりました。
例えば、英『ガーディアン』紙では「日本の万博キャラが恐ろしくも魅力的」と評され、アメリカの『WIRED』では「日本はまたしても大胆なデザインを見せた」と好意的な論調でした。これらの記事では、「気持ち悪い」という反応よりも「面白い」「一度見たら忘れられない」という評価が目立ちます。
特にアートやカルチャーに関心が高い層からは、「これが日本のサブカルチャーと前衛芸術の融合か」とポジティブな受け止め方が多く見られました。
アジア諸国での口コミと翻訳コメント
中国、韓国、台湾などアジア圏でも、ミャクミャクはSNSやメディアで広く紹介されました。中国のWeiboでは「奇怪但可爱(奇妙だけど可愛い)」というタグでトレンド入りし、日本のデザイン文化への関心の高さがうかがえます。
韓国ではネットニュースで「日本の万博キャラが話題騒然!」と報じられ、韓国のユーザーからは「ドラマに出てきそう」「日本はやっぱり自由だ」といった感想が寄せられました。
台湾でも「見るたびに好きになってしまう」「気味が悪いけどクセになる」と評価が分かれており、まさに日本と同じように賛否両論が巻き起こっている状態です。
以下は各国のSNSコメントの翻訳例です:
| 国・地域 | コメント(翻訳) | 備考 |
|---|---|---|
| 中国 | 「初めは怖いと思ったけど今は可愛い」 | Weiboより |
| 韓国 | 「ホラー映画のキャラっぽいけど気になる」 | ネット掲示板より |
| 台湾 | 「絶対に忘れられない顔」 | Facebookより |
「日本らしい」と受け入れる声も?
多くの海外メディアやユーザーがミャクミャクを「日本らしい」と感じた背景には、既に世界に知られている日本のサブカルチャーやアニメ、奇抜なファッション文化の存在があります。
たとえば、「ポケモンの奇妙なキャラ」「妖怪ウォッチの世界観」「村上隆のアート」といった、非日常的で大胆なデザインに慣れている層にとって、ミャクミャクはまさに「期待通り」の日本の創造物だったようです。
その結果、「日本がこういうキャラを出してくるのは普通」「むしろ普通すぎたらがっかりしていたかも」といった声もあり、日本の独自性を肯定的に捉えている様子が見受けられます。
国際的なアート界の評価はどうか
現代アートやデザインの専門家からも、ミャクミャクは興味深い作品として捉えられています。特に「変形するキャラ」「境界の曖昧さ」「有機的造形」といった特徴が、生命の多様性や未来の可能性を象徴するモチーフとして評価されているのです。
フランスやドイツのデザイン専門誌でも、「政治的・商業的な意図を超えた純粋な表現」という解説がされ、単なるマスコットではなく「未来社会を表現するメディア」として見られています。
これは日本国内とはやや異なる視点で、「不快感=失敗」ととらえるのではなく、「不快=問いを投げかけるアート」として評価しているのが特徴です。
世界が注目する「バズるキャラ」として成功?
SNS時代の今、注目されるキャラクターの条件として「バズる力(拡散力)」は非常に重要です。ミャクミャクはその点で大成功していると言えるでしょう。
発表当日から国内外のSNSで話題となり、TikTokやInstagramでも「#Myakumyaku」のハッシュタグを使った投稿が続出。英語圏では「creepy but cool(気味悪いけどカッコいい)」という評価が定着しつつあります。
また、ミャクミャクのぬいぐるみやキーホルダーは訪日外国人観光客の間でお土産として人気となっており、キャラクターとしての商業的価値も見逃せません。
世界的に「かわいい」や「かっこいい」だけではなく、「変わっていて話題になる」ことが評価される時代。そういった意味で、ミャクミャクは「世界で戦えるマスコット」として成功していると言えるでしょう。
なぜこのデザインが選ばれたのか?背景にある意図
万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」との関連性
2025年大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。この壮大なテーマには、医療、環境、テクノロジー、文化の進化など、あらゆる生命の可能性を追求するという意図が込められています。
このコンセプトに対し、ミャクミャクのデザインは一見ミスマッチにも見えますが、実は「生命そのものの構造」「水と細胞の融合体」という設定は、テーマに深く結びついています。
赤い球体は細胞や血管を表現し、青い顔は水の精霊をイメージ。つまり、「生命の源」と「進化の可能性」を可視化した存在がミャクミャクなのです。従来の“可愛いマスコット”では伝えきれない、生命の複雑さや多様性を象徴していると言えるでしょう。
単なるマスコットじゃない?メッセージ性の強さ
ミャクミャクには、単に「万博を盛り上げるためのキャラ」という役割以上のメッセージが込められています。それは、「多様性を認め、固定観念を打ち壊す」というアート的な意味合いです。
見た目が奇妙で、万人受けしないことを承知の上で、「他と違うことに価値がある」「多様な生命の表現を肯定する」という姿勢を体現しているのがミャクミャク。つまり、このキャラ自体が一種のメッセージなのです。
「受け入れがたいものにも意味がある」「自分と違う存在をどう受け入れるか」という問いを、キャラクターを通して社会に投げかけているのです。
批判も「戦略の一部」だった可能性
多くの批判を浴びたにもかかわらず、ミャクミャクは今や認知度抜群のキャラクターに成長しています。これは「炎上商法」とまでは言いませんが、「一度見たら忘れられない」「SNSで語られる存在」になることを狙った可能性は十分にあります。
実際、ミャクミャクの登場は全国ニュースに取り上げられ、ネット上でも長期間にわたってトレンドを維持。さらに、ぬいぐるみやキーホルダーなどのグッズも次々に展開され、「キモいのに売れる」という現象が起こっています。
注目を集めて記憶に残ること。それが結果的に万博の認知にもつながるのであれば、批判はむしろ「広告効果」として計算されていたのかもしれません。
万博での展開とグッズ戦略
ミャクミャクは、万博の広報だけでなく、今後さまざまな現場で活用される予定です。既に以下のような展開が始まっています:
-
イベント出演:地域の子ども向けイベントや商業施設での着ぐるみ登場
-
コラボ商品:文房具、飲料、ファッションブランドとのコラボ
-
公式アプリ:ミャクミャクがナビゲートするアプリもリリース予定
-
ミャクミャクダンス:子ども向けPR動画として公開され話題に
これらを通して、「気持ち悪い」から「親しみやすい」へと印象を変えていく長期的なブランディング戦略が進められているのです。
また、海外の観光客向けにもグッズ展開が予定されており、「お土産としてのインパクト」を狙った商品が人気を集めています。
「キモかわいい」は時代の流れ?
今の時代、「可愛い」は一つの型にはまったものではありません。「ゆるキャラ」ブームを経て、次に来るのは「キモかわいい」や「クセになる」存在感。ミャクミャクは、まさにこの時代の流れに合ったキャラクターだと言えます。
たとえば、SNSでバズったキャラ「ちいかわ」や「ズーラシアンブラス」の動物たちも、どこか不思議な見た目や設定がウケています。つまり、人々は“普通”や“典型”よりも、“ちょっとズレてて愛おしい”ものに惹かれ始めているのです。
ミャクミャクの登場は、日本のキャラ文化が次の段階に進もうとしている象徴とも言えるでしょう。
まとめ
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」は、その独特なビジュアルと強烈なインパクトから、国内外で賛否両論を巻き起こしました。「気持ち悪い」「怖い」といった声が多く上がる一方で、「クセになる」「記憶に残る」というポジティブな評価も確実に広がっています。
このキャラクターは、単なるマスコットではなく、「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマを体現する存在であり、見た目の奇抜さにも明確な意図があります。海外でも注目を集め、アート作品としての評価や、「日本らしさ」を象徴する存在として受け入れられています。
可愛いだけでは終わらない、“議論される”キャラクター。それがミャクミャクです。話題になることで大阪万博そのものへの関心を高め、多様な価値観や表現のあり方を社会に問いかける存在として、今後の展開にも注目が集まります。